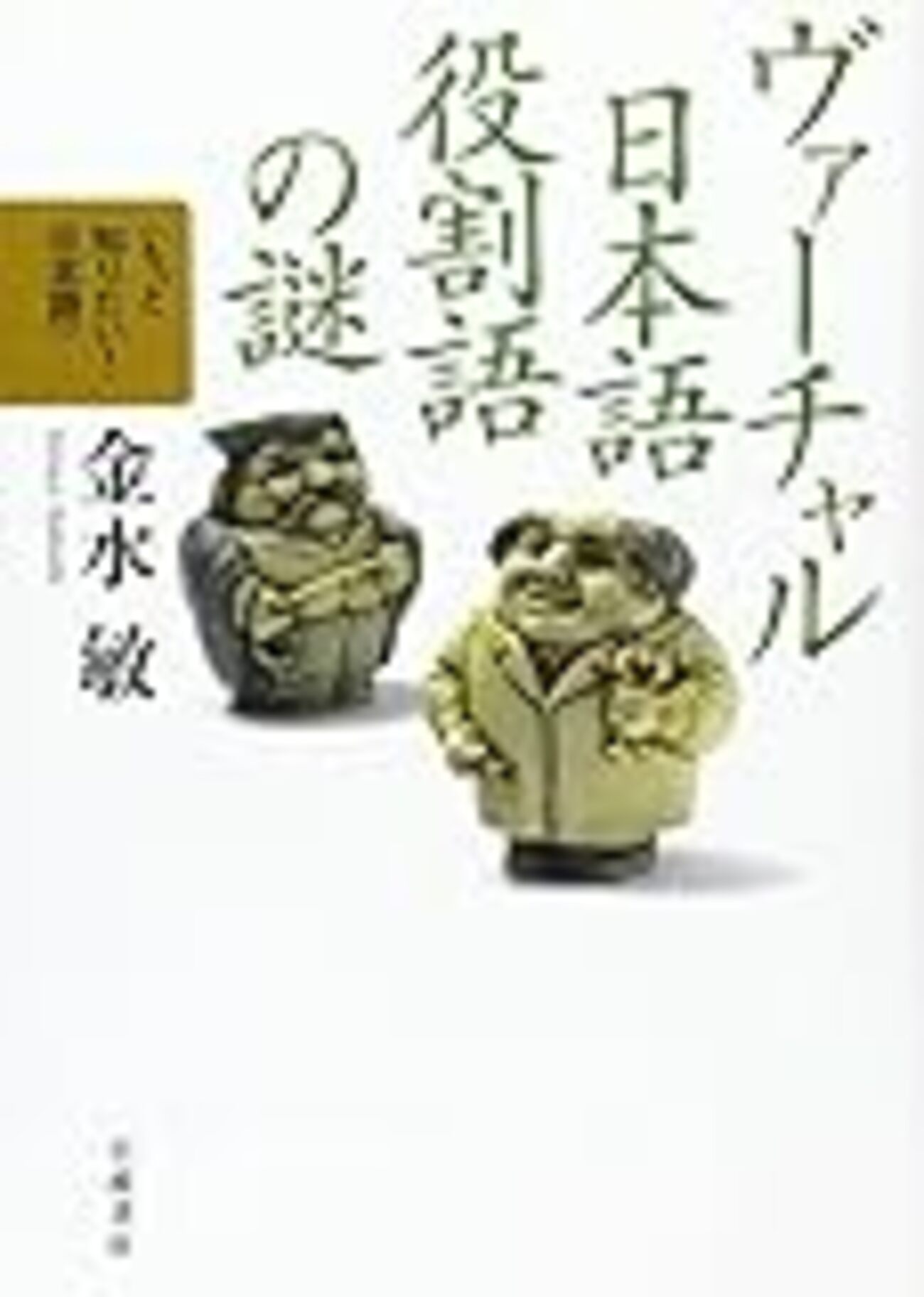1. はじめに
役割語に関する話題はWebでも定期的に見かけますので、簡単な読書案内を書きました。最初のバージョンは下記のブログ記事です。以降こちらのページで更新していきます。
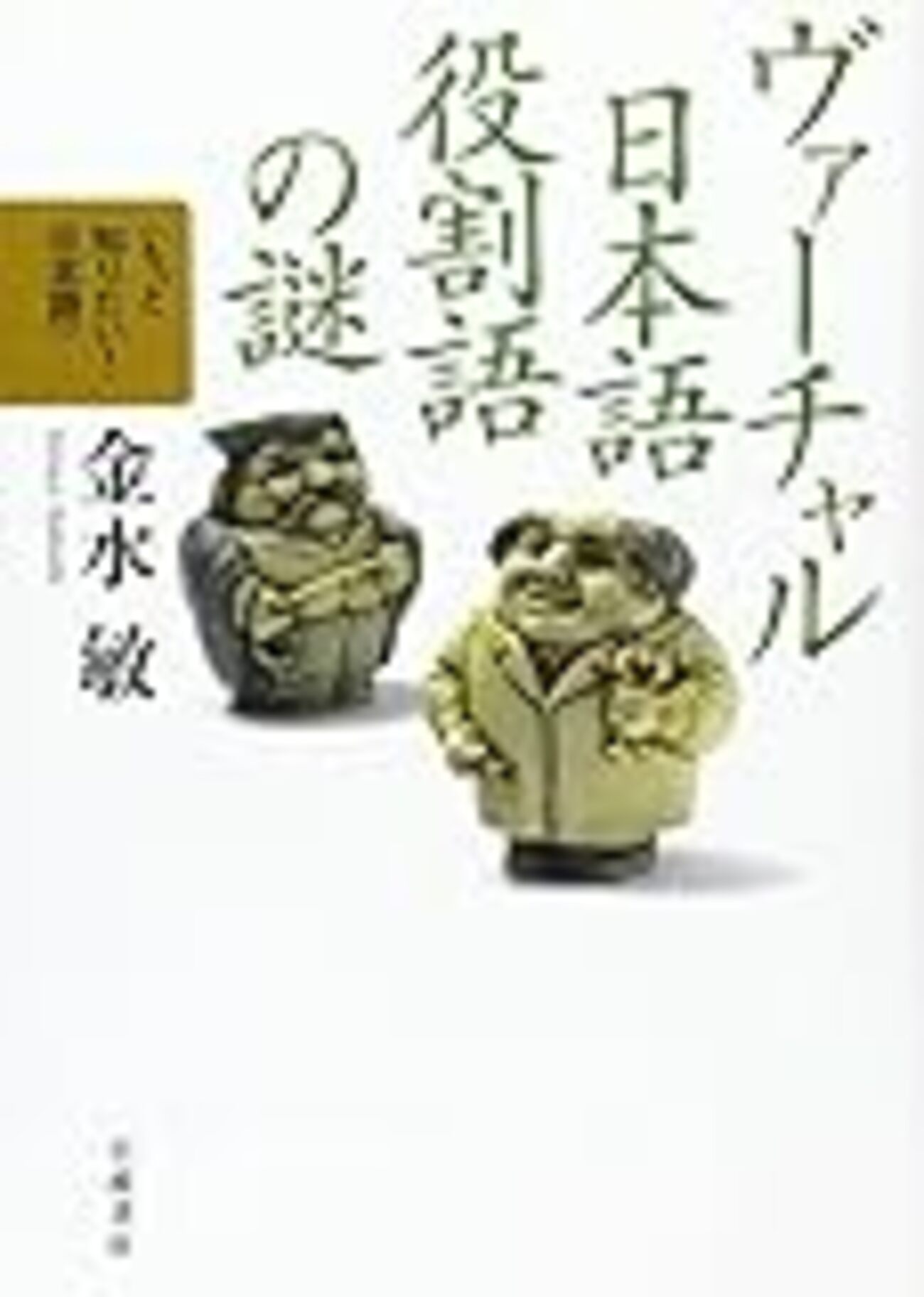
2. 基本
この手の話題に対する反応の中に「役割語」というキーワードがだんだん増えてきて日本語研究に携わるものとしては嬉しく思います。
ただ、役割語に関する基本文献はなんといっても下記の金水敏 (2003)『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』ですが、一般的にはこちらに目を通した方はまだそれほど多くないのかなという印象があります。
Title: ヴァーチャル日本語 役割語の謎
2023年に文庫版が出て、さらに手に取りやすくなったかと思います。こちらにはKindle版もあります。
ちょうど良いので、まず「役割語」の定義を本書から引用しておきましょう。
ある特定の言葉づかい(語彙・語法・言い回し・イントネーション等)を聞くと特定の人物像(年齢、性別、職業、階層、時代、容姿・風貌、性格等)を思い浮かべることができるとき、あるいはある特定の人物像を提示されると、その人物がいかにも使用しそうな言葉づかいを思い浮かべることができるとき、その言葉づかいを「役割語」と呼ぶ。
(金水 (2003): 205)
最もコアになる概念の明確な定義が本の終わりの方に出てくるので、もしかしたらここまで読み進めていない人もけっこういるのかもしれません。ただ、この定義を先に読まなくても本書を読み進めるのに支障はないでしょう。
ちなみに、金水敏(編) (2014)『〈役割語〉小辞典』のはしがきでもこの定義が紹介されています。
Title: 〈役割語〉小辞典
これは「ありんす」「ざあます」「わたくし」のように役割語に強く関わる語ごとに引ける小さい辞典です。小さいながらも語誌についてかなり詳しく書いてありまして、表現の由来が気になる方も面白く読めると思います。「アルヨことば」「書生語」といった役割語名索引も付いていますし、具体例が非常に豊富で引用出典一覧を見ているだけでもなかなか楽しいです。
中国に関係のあるキャラクターと「アルヨことば」の結びつきを題材に外国人/異人へのまなざしとことばの結びつきについて詳しく考察しているものとして金水敏 (2014)『コレモ日本語アルカ? 異人のことばが生まれるとき』があります。
Title: コレモ日本語アルカ?異人のことばが生まれるとき
下記の記事でも紹介しました。
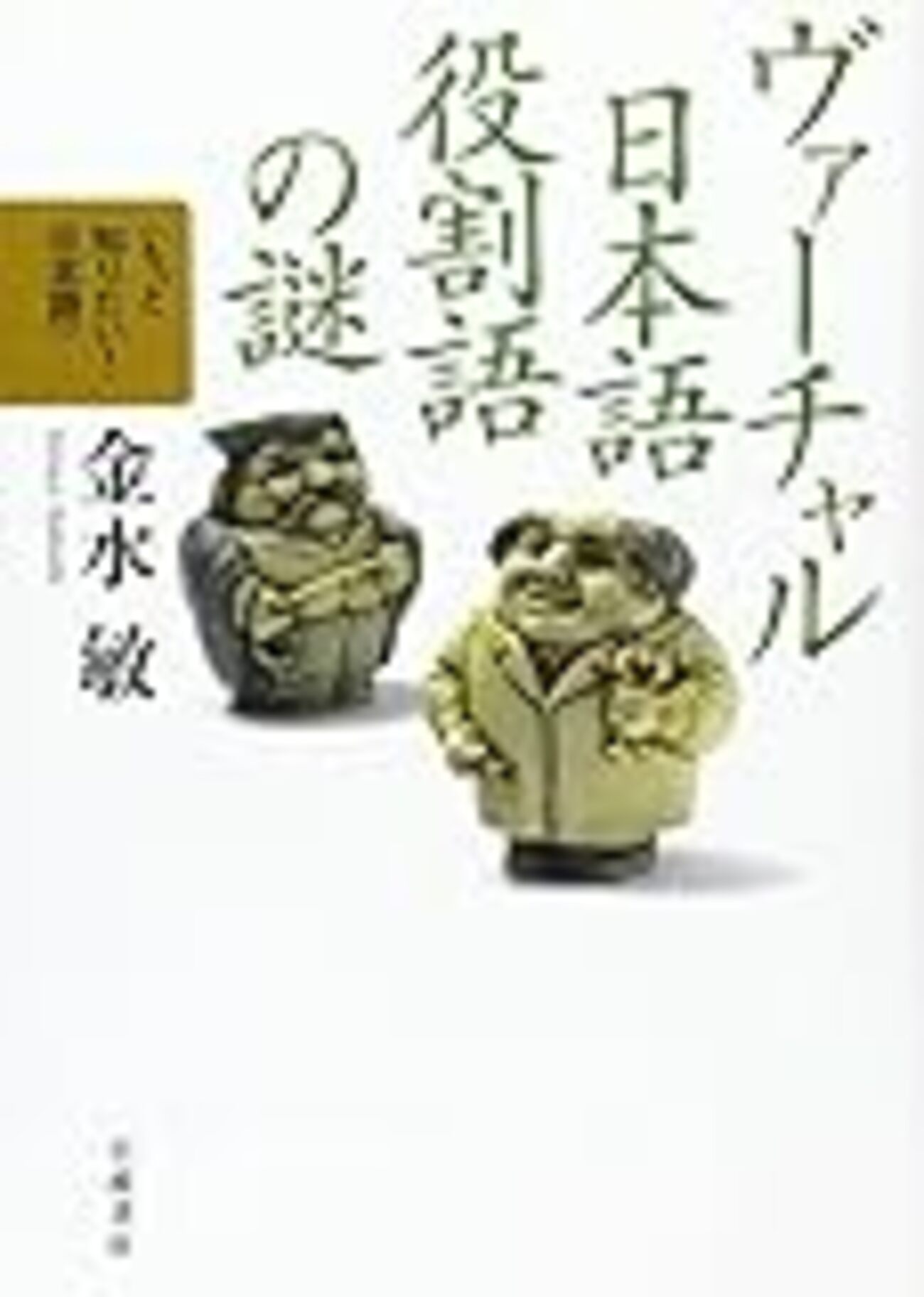
本書からの重要な引用をこちらにも載せておきます。
…。<アルヨことば>をさべる中国人のキャラクターの、とぼけた味わいが好ましかった。 (中略) しかし今、その発生と継承の歴史を調べていく中で、<アルヨことば>の使用と中国人に対する日本人の侮蔑意識という政治的文脈とが分かちがたく結びついていることを知らされた。またその研究の道筋で、満州ピジンの存在も知った。
(中略)
本書に記してきたことを踏まえるなら、もはや政治的な文脈への配慮なしに軽々に<アルヨことば>を用いたり論じたりすることは慎まれるべきである。本書に記したこのことばの背後にある歴史についての知識や、またそれに伴う配慮が、新たな日本の常識になることを願ってやまない。 その一方で、子供のころから好きだった<アルヨことば>の歴史をきっちりと描き出し、ある意味で永遠に供養したいという願いもまた本書の執筆を強く支えていたのである。
(金水 (2014): 215-216,強調は田川)
こちらも文庫版が出ました。
ここで紹介した3冊は、いずれも日本語学や言語学の知識がまったくなくてもかなり楽しめると思います。私の印象では、 webでこの手のことが話題になる時に出てくる疑問のかなりのものについては、上記のいずれかの本に答えあるいはヒントがあります。 Webで本書の内容に関するマンガやまとめを見かけることがありますが、概要をつかむには良いものの、議論の詳細や具体例、データ、資料の紹介には限界があるので、やはり本がおすすめです。
また、「なんかマンガのキャラが変わった言葉づかいをするやつでしょ」とは簡単にまとめてしまえないおもしろい/奥深い問題がいろいろあることをいろいろな方に味わってもらえればと思います。
3. キャラと定延利之氏の研究
上で紹介した金水氏の研究は役割語の「ことば」の側面(由来や変遷)にかなりウェイトをおいた記述がなされていますが、役割語のもう一方のポイントである「キャラ(クター)」に焦点を当て、役割語に限らず言語やコミュニケーションとの結びつきについて面白く重要な研究を出し続けている研究者として定延利之氏がいます。
キャラについては、専門の方でなくても面白く読める本が出ています。定延利之 (2011)『日本語社会のぞきキャラくり』です。
定延氏はキャラ語尾にキャラコピュラとキャラ助詞があることを発見するなど役割語研究が始まった早い段階から重要な研究を発表していますが、この本では役割語とはちょっと異なる観点からキャラクターとことばの結びつきについてさまざまな考察がなされています。
役割語研究でよく取り上げられるようなフィクションの登場人物のセリフだけでなく、我々の日常の風景によくあるような会話の例もいろいろ出てきて楽しかったりどきりとさせられたり。定延氏の長年の研究テーマの1つである音声的特徴(イントネーションとか)と文法・コミュニケーションの関わりについてもたびたび言及があるのも面白いですね。
キャラ研究についてはその後、定延利之(編)『「キャラ」概念の広がりと深まりに向けて』という論文集が出ています。こちらは専門的な内容・分析も多いので人によっては読むのはちょっと大変かもしれません。
Title: 「キャラ」概念の広がりと深まりに向けて
下記の研究書『コミュニケーションへの言語的接近』でも、それほど多く取り上げているわけではないのですがキャラとコミュニケーションの結びつきについて専門的な分析がなされています。
Title: コミュニケーションへの言語的接近
4. おわりに
役割語は、マンガや小説等のフィクション翻訳等でよく話題に上がりますし、そちらに興味のある方々に楽しんでもらいながら今後も認知度が上がっていけばいいなと思います。一方、 文章・書きことば・テクストが関係することを考える上ではもはや避けて通れない問題ですので、専門的には日本語学・言語学が直接関わる分野以外の方々にも広く知ってほしいところです。
関連記事